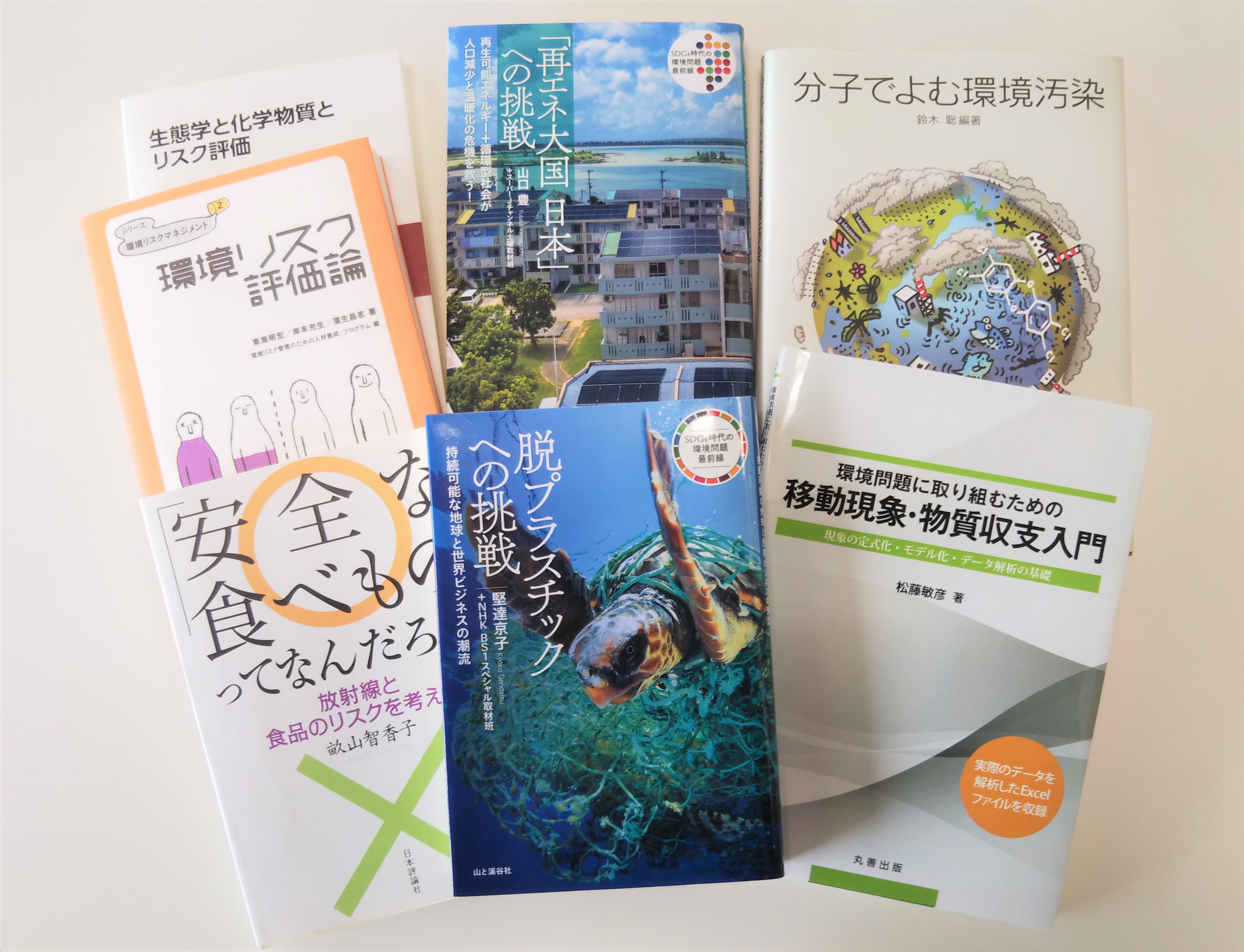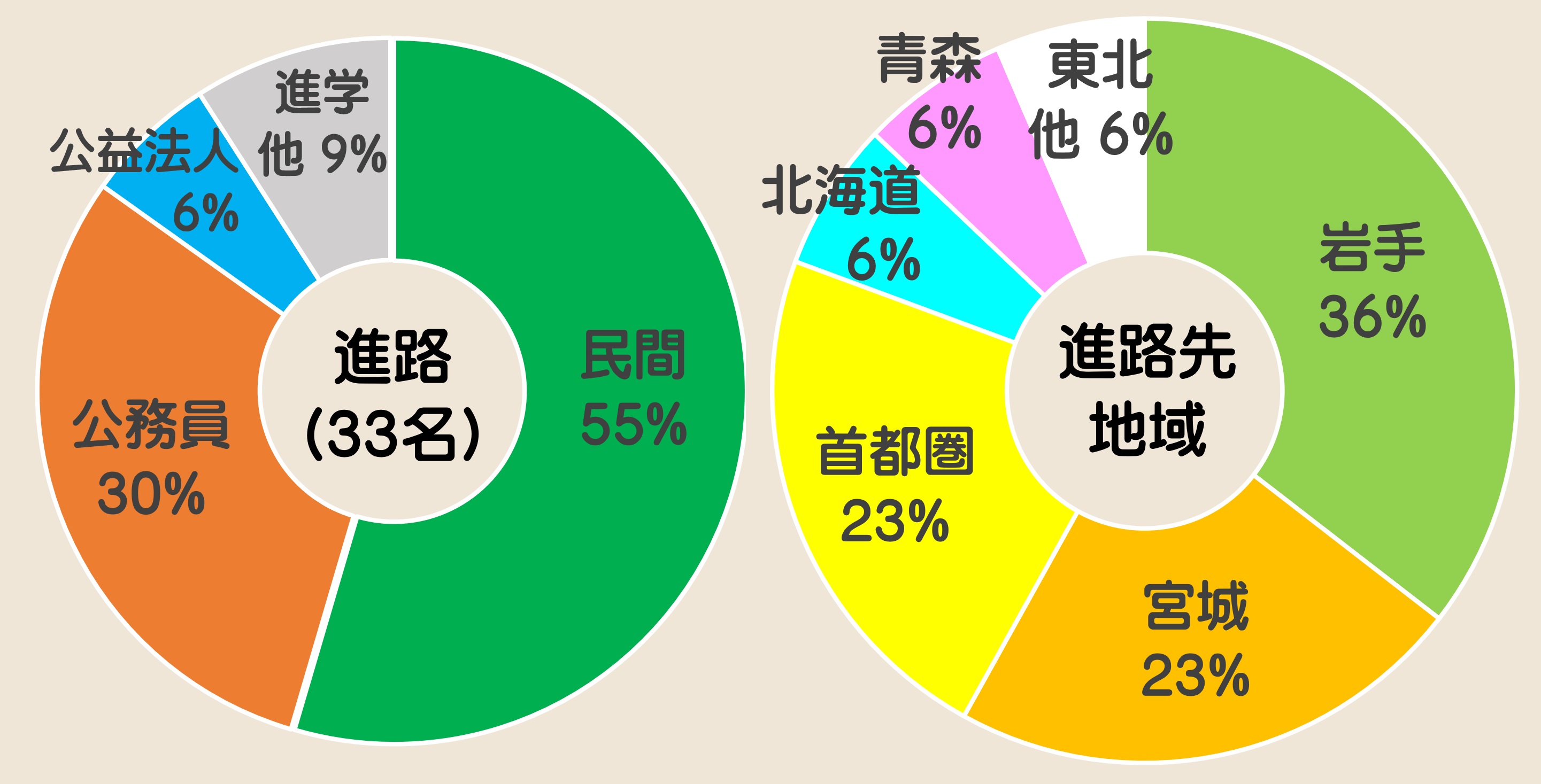ニュース
2025.12.18 行事更新
研究室紹介
化学物質から環境と政策を考える
環境と物質社会の共生を目指し, 広い意味での化学物質による地域の環境問題や健康問題をテーマに, 予防原則と利便性の両面から行政施策や企業活動へ貢献できる研究に取り組んでいます。
日本では高度経済成長期に水銀やカドミウム等による地域の環境問題が各地で表面化しました。これらの問題に対処するため公害対策基本法(現・環境基本法)が制定されました。同じ頃,
西日本を中心に有害物質(ポリ塩化ビフェニル, PCB)が混入した食用油を摂取した人々に深刻な健康被害が発生しました(カネミ油症事件)。この事件を契機に,
化学物質には法規制による審査と管理(化審法)を義務付けました。
地球上にはこれまで2億を超える物質が合成され, 今も数秒に1個のペースで新物質が誕生していると言われます。便利な製品が次々と製造される一方で,
こうした物質がこの先10年, 20年の間にヒトや生態系へ思わぬ影響を及ぼし過去の公害と同様の社会問題を引き起こすかもしれません。
当研究室は地域の環境汚染や未規制物質の隠れたリスクを発見し, 環境問題や健康被害へ発展することを未然に防ぐ研究を進めています。具体的には, 北上川の水質汚染,
日用品や生活必需品とヒト・生態系影響の関係, 東北沿岸に漂着するプラスチックゴミなど, 地域からグローバルな環境問題に触れ, リスク削減に向けた行政対応や企業活動のあり方を検証します。
国内では低炭素社会の実現に向けて火力発電(石炭やメタンの燃焼)の高い依存度が課題となっています。新エネルギーへの転換が求められる中, 化学的視点からカーボンニュートラル(CO2収支ゼロ)になり得る政策の提案に取り組んでいます。
普段何気なく使っている商品やエネルギーの「ゆくえ」を知り, 物質が環境との共生を目指すうえでリスクとなり得るのか議論を深めます。
※リサイクルペーパーに関する研究成果が国立環境研究所の環境情報メディア「環境展望台」, 本学「ウェブサイト」で紹介されました。
生活排水による水環境への影響調査(北上川)

東北沿岸のプラスチックゴミの問題について (写真は岩手県浪板海岸)
何を学ぶのか?
現在, 社会には様々な製品や未規制の物質が存在しています。化石燃料で作ったエネルギーを使うとCO2が発生します。これらの製品や物質についてヒトや生態系への影響(リスク)を統計的に数値化して, 許容量と比較することが環境リスク学の基本となります。
身につく力:リスクや社会問題を科学的根拠に基づき判断する能力が身につきます。限られたリソース(ヒト/モノ/カネ)の中で, 政策・緊急時対応などの優先順位づけができます。
活かせる職業:自治体や企業コンサルタントでリスク・コミュニケーションを必要とする部署など。
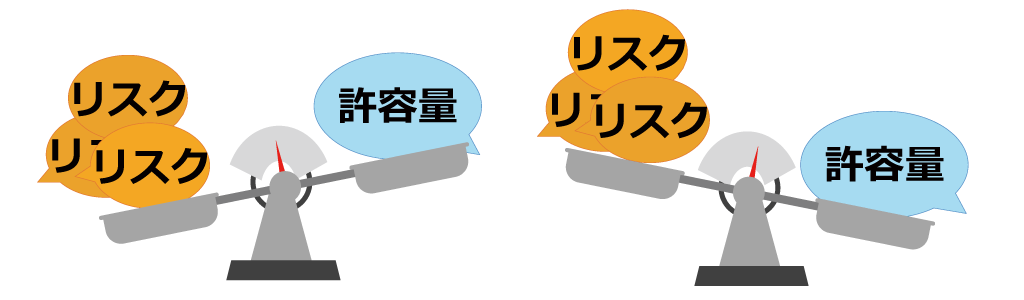
リスクと許容量を統計的に判断
演習や特別研究(卒論)・研究室配属について
ゼミ(演習1・2):現代社会が抱える環境問題やリスクを扱ったテキストを用いた発表会(輪講)をおこないます。発表者はテキストの担当内容についてレジュメを作成・解説します。他の参加者はレジュメの内容を中心に質問や意見を出し合います。年末には中間発表会を開き,
卒論に向けたテーマを少しずつ固めていきます。
卒論:サンプル採取や濃度測定といった実験も取り入れて調査を進めることもあります。自然科学系の実験は未経験の学生も多いと思いますが, 研究室に配属後で構いませんので
環境科学実験(集中講義)を履修すると必要な理論や知識を網羅できます。
また実験によるアプローチではなく、文献から環境や健康への影響を評価するテーマもあります。データ解析が「鍵」になるので統計やエクセルによる演算に慣れておきましょう。